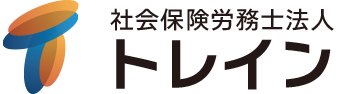若年人材確保のための給与制度を考える
2025.7今回は、初任給の見直しをはじめとした若年人材確保のための給与制度の在り方について考えます。
本稿でいう「初任給」とは、新卒者の給与に限らず、中小企業における若年者を中途採用する際の募集給与額全体をさします。
1.若年人材確保のための初任給の見直しの必要性
当人事・労務便り5月号でもお伝えしました。今年に入ってからの雇用状況や春闘における賃上げ状況、そして大手企業の初任給引上げの報道を見ると、中小企業においても新卒社員をはじめ若年層の人材を確保するにあたっては、一定の給与水準の引き上げは避けられない状況であると言えます。
2.初任給の見直しにあたり考えるべきこと
初任給を見直すにあたり、会社としては(1)どの水準まで上げるのか?賃上げの基準をどう考えるか?(2)既存若年社員との均衡をどのように保つのか?(3)膨れ上がる人件費をどのように抑えるのか?を考えなければなりません。
3.初任給、どこまで引き上げる?引き上げ額は何を基準に決定する?
給与額の見直しやベースアップにあたり、トレインでは次の二つの指標を参考基準としています。
いずれも賃金の年齢別対前年増減率や職種別時給額の平均値が集計されており、ベースアップ額や職種別の給与額設定を考える際に月額換算して参考にしています。
- (1)
-
「賃金構造統計」賃金構造基本統計調査による職種別平均賃金(時給換算)
https://www.mhlw.go.jp/content/001294218.pdf
「賃金構造統計」速報:年齢別学歴別賃金グラフ
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2024/dl/sokuhou.pdf
- (2)
-
「職業安定統計」職業安定業務統計の求人賃金を基準値とした一般基本給・賞与等の額(時給換算)
4.既存若年社員の給与との均衡を考える
初任給の引き上げで問題となるのは、既存若年社員との給与の逆転現象です。既存社員が給与の逆転現象により辞めてしまっては本末転倒です。若年人材は、採るだけでは意味がなく、採用後、育て、戦力として定着させてこそ企業としての目的が達成できます。既存社員との均衡を考えると、会社の給与テーブルを全階層の社員で初任給の引上げに合わせて引上げ、または見直しをすることが必要となります。
5.若年者のこれからの人事評価、処遇決定
若年社員が会社に求めるものには「仕事のやりがい」、「プライベートの充実」、「そこそこの収入と福利厚生」などのほか「仕事を通して自分が成長できるか」があります。会社全体の給与テーブルの見直しの際には、成果よりもプロセスやスキルの向上など育てるための目標管理や人事評価に主眼を置く日本での従来からの職能主義により、入社から10年程度は年を追うごとに給与が少しずつでも着実に上昇する給与体系、スキル向上を促す手当の支給など給与制度、評価制度の見直しが必要かもしれません。
6.膨れ上がる若年者の人件費をどこで調整するか
初任給をはじめ入社から一定年数までの若年者の給与を引き上げるとなると、会社全体としての人件費が膨れ上がることになります。これを抑制するとなると必然的に、ミドル・シニア層の給与や処遇決定の制度の見直しが必要となります。
※次回以降でこれからのミドル・シニア層の給与制度の在り方と活用について考えます。